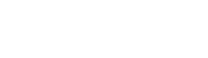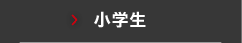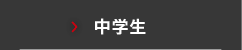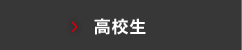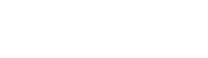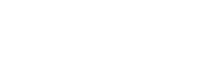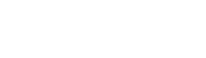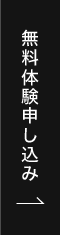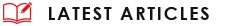TOP > BLOG
2018.02.16
カテゴリー: その他
僕は、「時間とは命」と捉えています。
1時間の時間を過ごした=1時間分の自分の命を使ったと考えています。
この1時間が誰かと過ごしたとすると、相手の命も使っていると考えています。
と、考えると無責任な時間の使い方はできないです。
生徒たちとも時間の使い方については、よくディスカッションしています。
1セッションは60分~90分。この時間をどれだけ価値のあるものにできるか。
日々過ごしている時間をどれだけ価値のあるものにできるか。
いつも考えながら、指導にあたっています。
2018.02.16
カテゴリー: その他
プランの設計ができたら、次は実行(Do)になります。
計画を立てたが、実行できない or 続かない or やり切れないなど、計画通りに進まないことが起こりえます。
その原因を考えると
①そもそも自分が達成したいと思っていない。
②自身の達成度を見える化していない。
この2つかと思っています。
①は僕の指導ではStarを設定すると言いますが、Starはキラキラと光り輝いている自分を指しています。ただ、達成したいだけでなく、「ワクワク」など感情が伴う目標設定を指しています。
②は自分が実行したことを、日々記録として残していくことになります。その時に第3者を巻き込む方が継続できる可能性が高まります。
S-PDCAでは、成果を出すことをもっとも重要視しています。成果を出す確率を高めるための工夫を散りばめています。
2018.02.12
カテゴリー: その他
答えは、簡単で「やる本人が80点取れる予感がする計画を創ること」です。
数学で80点を取れている姿=Star
※今回はStarの設定ができていると仮定します。
Starができたら計画を立てる=Plan
このPlanを立てる時のポイントは2点だけです。
①助言やアドバイスは求めてもよいが、抽象性と具体性を合わせもったプランを自分で決める。
②できたプランを周りの人に伝えて納得感があるか確かめる。
ここからは実例を記載します。
【数学のテストに対して80点を取るためのプラン(草案)】
①学校のワーク・プリントをすべて解けるようにする。
②学校のワーク以外の問題集も解き、なるべく多くの問題に触れておく。
ここまで生徒だけで決めてもらいました。「どう決めていいかわからないんだけど」と助言を求められたので、「ググったら?」と助言しました。僕がこの段階で手を貸したのはこれだけです。
生徒が色々なページを見ながら45分かけて決めてくれました。これだけでも立派だし、80点取れそうな気もします。大きな戦略として間違っていないと感じます。
ただ、ここからが重要で、実際の行動に繋がるようにもう少し「具体性」を持たせる必要があります。
例えば①の「すべて解けるようにする」は「抽象的」です。どうなればすべて解けるようになったといえるのか。
どんどん具体的に一緒にしていき、たどり着いたプランは
【数学のテストに対して80点を取るためのプラン(本案)】
①学校のワーク・プリントをすべて解けるようにする。
②学校のワーク以外の問題集も解き、なるべく多くの問題に触れておく。
・セッション毎に「プチテスト」を行う(同じ問題を抜粋して解く)
・「プチテスト」後に、生徒が僕に「解説」を行う。僕の突っ込みにすべて答えられて〇
・そもそも毎日、数学の問題に取り組み、僕にその成果をラインで送る。
となりました。生徒も納得感が強くなったようでした。
自分ですべて決めることは重要です。自分で決めたことだからこそ、「やってみよう!!!」と思うことができます。
そして、このプランを保護者さんに伝えて、保護者さんも納得感があるとのことでスタートしています。
このプラン設計も、将来は自分だけで、できるように指導していきます。
②に続きます。